10年前の夏、ちょうど福島でドキュメンタリーを撮り始めた頃、東京オリンピックが決まった。ナオトさんと私はテレビを見ながら、「ああ、オリンピックの影で福島のことは忘れられてしまうね」と話していた。その後、オリンピックに合わせて、福島の「再建」は急ピッチで進んでいった。帰還困難区域にある夜ノ森駅が再建されて、無理やり道が通された。しかし2020年、コロナの蔓延でオリンピックが延期され、新しい建物は虚しく立っていた。「復興五輪」の入口として、福島は華々しく世界にお披露目される予定だった。ナオトさんは「これのどこが復興だ?建物が新しくなっただけで、人が帰ってねえべ。『復興五輪』なんてPRに使われて、地元からしたら、ふざけんなだ」と言っていた。そして震災から10年、色々なセレモニーが行われた。しかし参加した地元の人たちは少なく、ほとんどがマスコミだった。「震災10年が終わったら、また忘れられるな」と、ナオトさんはつぶやいた。でも原発事故は収束からほど遠い。あふれかえっている汚染水が太平洋に垂れ流されようとしている一方で、CO2削減が呼びかけられ、 全国で原発再稼働がじわじわと進められている。
そんな矛盾の渦中にある福島で、ナオトさんは相変わらず牛の世話をし、ヘビに卵を食べられながらも、野鳥の巣箱を作り続けている。おそらくナオトさんと私が生きているあいだに原発の問題は終わることはないだろう。人が置いてきぼりになっている形ばかりの「再建」を横目に、淡々といのちをつないできたナオトさんと動物たち。
原発事故から10年を経て、一旦、この映画をまとめようという話がプロデューサーの山上さんから出た。そして最後の取材には、ちゃんとカメラマンの辻さんに撮ってもらった方がいいと言われた。なぜなら私が自分でずっと一人で撮影してきたから、ナオトさんと私の関係性が画面に写っていないからだ。福島がまだ終わらない状況が続いている中、この映画をまとめることに、私は罪悪感を感じながらも、撮影を続けた。「原発事故から10年経って、今、何を思いますか?」と、私はナオトさんと半谷さんたちに尋ねた。そして彼らから驚愕の答えを聞いた。それはこの映画の中で、観客の皆さんに確かめてもらい、考えて欲しい。

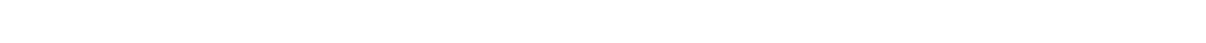




















「福島原発事故で、本当に日本の半分が、あるいは全部が壊滅してもおかしくない寸前だった。そのような非常に厳しい環境の中で動物の世話しながら暮らすナオトさんの勇気に感服し、動物たちや自然をけがしてしまった人間の罪深さを改めて感じた」
「ナオトさんの言う『ムカつくだっぺ』『ふざけんなって言いたくなる』にすっかり同調しながら見た。でも、その視線を借りている自分は、もしかしたら、ナオトさんの視線に入っている側なのかもしれない。そして、この戸惑いや危うさを感じるのが、実に久しぶりであるという情けなさを噛み締めておきたい」
「この町、人、動物たち、ここにあった生き物たちの美しい営みは、置き去りにされてしまった、のではない。わたしたちが置き去りにしたのだ。どうすればいい。どんな答えも、完全な善でも悪でもない。だから考え続ける」
「損得を超えたところで、捨てられかけた命の重さを問い、この社会がやるべきことを暗に示す。示し続ける。ナオトさんの足掛け10年に及ぶこれまでのブレない歩みは、アーティストが作品にすべてをこめて訴えるように、捨てられた生き物たちの命を全うさせることをもって社会に問いかける、きわめて息の長いデモンストレーションとも言える」
「社会から棄てられたもの言わぬ者たちの世話をして生きる男。十年前に目撃した男の生き様は変わらず続いていた。彼の周りで亡くなった命、誕生した命。そのすべてが尊い。原発事故が何を奪ったのか、寡黙な映像は静かにその問いを僕の喉元に突きつける」